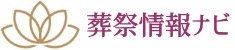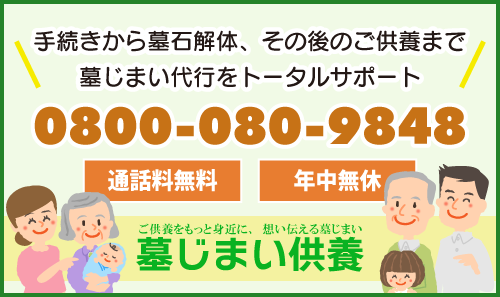七回忌・十三回忌など年忌法要の種類と意味
[掲載日]2025/10/08 56 -

葬儀や四十九日、一周忌、三回忌を終えると、故人を偲ぶ節目の行事として「年忌法要(ねんきほうよう)」が続きます。
七回忌・十三回忌・三十三回忌など、聞き慣れた言葉ではありますが、それぞれの意味や時期を正しく理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。
この記事では、年忌法要の基本知識から、回忌ごとの意味・時期・準備のポイントまでを詳しく解説します。
年忌法要とは?

年忌法要とは、故人の命日を基準にして毎年、または節目の年に行う供養のことです。
仏教では、命日を「祥月命日(しょうつきめいにち)」と呼び、この日に供養を行うことで故人の冥福を祈ります。
- 一周忌・三回忌までは特に重要な節目
- 七回忌以降は「先祖供養」の意味合いが強くなる
- 家族の絆を再確認する場でもある
年忌法要の種類一覧(スケジュール表)
| 回忌名 | 行う時期 | 故人逝去からの経過年数 | 特徴・意味 |
|---|---|---|---|
| 一周忌 | 1年目 | 1年後 | 最初の年忌法要。親族・友人も招く。 |
| 三回忌 | 2年目 | 2年後 | 親族中心。節目の供養。 |
| 七回忌 | 6年目 | 7年目 | 親族中心。次第に規模を縮小。 |
| 十三回忌 | 12年目 | 13年目 | 故人が“家の守り神”になるとされる。 |
| 十七回忌 | 16年目 | 17年目 | 地域によって行う場合と省略する場合あり。 |
| 二十三回忌 | 22年目 | 23年目 | 故人への供養が薄れる時期。簡略化されやすい。 |
| 二十七回忌 | 26年目 | 27年目 | 家族単位で静かに供養する。 |
| 三十三回忌 | 32年目 | 33年目 | 「弔い上げ」。最後の年忌法要とされる。 |
※仏教では亡くなった年を「一回忌」と数えるため、三回忌=2年後、七回忌=6年後に行います。
七回忌の意味と特徴
七回忌は、故人が亡くなって6年後に行う法要です。
三回忌までの悲しみが落ち着き、供養が「家族の行事」として定着していく頃です。
- 親族中心で行うことが多い
- 友人・知人は招かない場合も多い
- 一周忌・三回忌を兼ねて永代供養に切り替えるケースも
【僧侶へのお布施目安】
3万円〜5万円程度。会食がない場合は「お膳料」を別途包みます。
十三回忌の意味と特徴
十三回忌は、故人が亡くなって12年後に行う法要です。
仏教では「故人が仏の世界で守り神となる」とされ、家族にとっても精神的な節目となります。
- 七回忌よりもさらに小規模化(親族のみ)
- お墓参り・供花・お供えを中心に行う場合も多い
- 法要のあとは会食やお茶会などで思い出を語ることが多い
【ポイント】
この頃から「年忌法要=形式よりも心で供養」という傾向に変わっていきます。
十七回忌・二十三回忌・二十七回忌
十三回忌以降の法要は、地域や家の考え方によって開催・省略が分かれます。
- 十七回忌(16年後):僧侶を呼んで供養するか、墓前で家族のみで手を合わせる。
- 二十三回忌(22年後)・二十七回忌(26年後):親族の集まりが難しい場合、法要を簡略化して個人供養とする。
【最近の傾向】
三十三回忌までを節目とし、それ以降は「永代供養」へ移行する家庭が増えています。
三十三回忌の意味と「弔い上げ」
三十三回忌は、故人が亡くなって32年後に行う最終の年忌法要。
「弔い上げ(とむらいあげ)」とも呼ばれ、ここで正式に先祖の一員として祀られることになります。
- 仏教では「三十三年で霊が成仏する」とされる
- 墓碑に「○○家之墓」として合祀することも多い
- 法要後に仏壇や位牌を整理・統合するケースも
【例文(喪主挨拶)】
本日は○○の三十三回忌にあたり、ご多用の中ご参列いただき誠にありがとうございます。
長きにわたり皆さまに見守っていただき、心より感謝申し上げます。
故人も安らかに眠っていることと思います。
年忌法要の準備と進め方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 命日またはその前の週末に設定 |
| 会場 | 寺院・自宅・墓地など |
| 僧侶 | 読経依頼(お布施・お車代・お膳料) |
| 案内状 | 2〜3週間前までに送付 |
| 供物・供花 | 果物・菓子・生花など |
| 会食 | お斎または軽食を準備(近年は省略も可) |
| 返礼品 | 3千〜5千円程度(タオル・菓子・お茶など) |
年忌法要の服装マナー
| 立場 | 服装 |
|---|---|
| 喪主・遺族 | 正喪服または準喪服 |
| 参列者 | 準喪服(黒・濃紺・グレー) |
| 季節 | 夏は薄手のブラックフォーマルで可 |
三十三回忌などでは略喪服でも失礼にあたりません。
ただし、明るい色の服や光沢のある素材は避けましょう。
年忌法要を省略する際の供養方法

最近では核家族化や遠方の親族の増加により、法要を省略する家庭も増えています。
その場合は、以下のような代替供養が一般的です。
- 墓前で手を合わせる
- 自宅で家族だけの焼香・お供え
- 永代供養・合同供養に切り替える
- 菩提寺に回向(えこう)を依頼する
「形式を簡略化しても、故人を想う心を絶やさないこと」が何より大切です。
まとめ|年忌法要は“感謝と継承”の儀式
年忌法要は、故人の冥福を祈るだけでなく、家族がつながりを再確認するための大切な時間です。
- 一周忌・三回忌は大規模、七回忌以降は家族中心
- 三十三回忌は「弔い上げ」として最終供養
- 時代に合わせて形式を柔軟に、省略も可能
形にとらわれすぎず、感謝と敬意を持って供養することが、最も尊い「年忌法要」のあり方といえるでしょう。