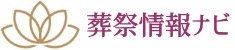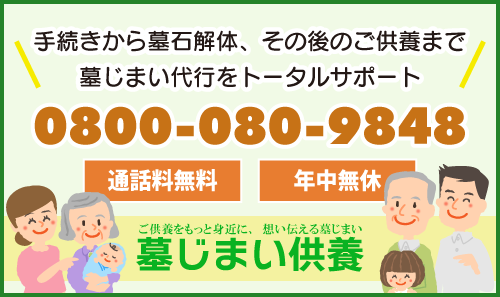葬儀後に必要な手続き一覧|死亡届・相続・名義変更まで完全ガイド
この記事は約 3 分で読めます
[掲載日]2025/10/06 52 -
[掲載日]2025/10/06 52 -

葬儀が終わっても、遺族には多くの公的・民間の手続きが残っています。
悲しみの中で複雑な手続きを進めなければならないのは大きな負担ですが、期限があるものも多く、早めの対応が欠かせません。
この記事では、葬儀後に行うべき手続きを時系列で整理し、必要書類や注意点をわかりやすくまとめます。
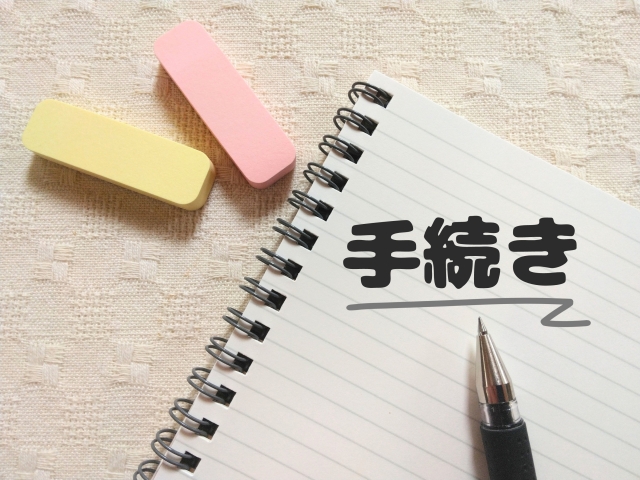
葬儀後の主な手続きスケジュール
| 時期 | 主な手続き |
|---|---|
| すぐに行う | 死亡届の提出、火葬許可申請 |
| 1〜2週間以内 | 健康保険・年金の手続き、公共料金の名義変更 |
| 1カ月以内 | 銀行口座・クレジットカードの解約、生命保険の請求 |
| 3カ月以内 | 相続放棄・限定承認の手続き |
| 4カ月以内 | 準確定申告(個人事業主など) |
| 半年〜1年以内 | 相続税の申告・納付、各種契約の整理 |
死亡届と火葬許可証の手続き
死亡届
- 提出先:死亡地・本籍地・届出人の住所地の市区町村役場
- 提出期限:死亡の事実を知った日から7日以内
- 必要書類:死亡診断書(医師が発行)
火葬許可証
死亡届と同時に火葬許可証の交付を申請します。
葬儀社が代行することが多いですが、許可証がないと火葬できません。
健康保険・年金の手続き
健康保険
- 故人が国民健康保険加入者の場合:役所で「資格喪失届」を提出
- 健康保険証を返却
- 葬祭費・埋葬料の申請(支給額:3万〜7万円程度)
年金
- 提出先:年金事務所または市区町村役場
- 必要書類:年金証書・死亡届書類・戸籍謄本
- 故人が年金受給者の場合は「年金受給停止」の手続きが必要
生命保険の請求
生命保険に加入していた場合は、保険会社に連絡し、請求手続きを行います。
- 請求期限:多くの保険会社で3年以内
- 必要書類:死亡診断書のコピー、保険証券、本人確認書類、戸籍謄本
保険金の支払いまでには1〜2週間かかるのが一般的です。
銀行口座・クレジットカードの手続き
銀行口座
死亡が確認されると口座は自動的に凍結されます。
葬儀費用などの支払いで一時的に資金が必要な場合は、代表者を決めて遺産分割協議後に手続きを行います。
クレジットカード
カード会社に死亡の旨を伝え、利用停止と解約を行います。年会費が自動引き落としされる前に早めに連絡しましょう。
公共料金・契約サービスの名義変更
- 電気・ガス・水道
- 固定電話・携帯電話
- インターネット回線・NHK
- 新聞・郵便物の転送
- 賃貸契約・自動車保険・クレジットカード引き落とし口座
これらは引き落としや請求トラブルを防ぐため、できるだけ早めに変更を行うことが大切です。
相続関連の手続き
遺言書の確認
まずは遺言書の有無を確認します。封印されている場合は家庭裁判所で「検認」手続きが必要です。
相続放棄・限定承認
- 相続放棄:借金などの負債を相続しない手続き
- 限定承認:財産の範囲内で負債を返済する手続き
いずれも3カ月以内に家庭裁判所へ申立てが必要です。
相続税の申告
- 相続税が発生する場合、10カ月以内に申告・納税が必要
- 税理士に相談して早めに準備を進めましょう
準確定申告(個人事業主・自営業の場合)
故人が事業を行っていた場合、死亡から4カ月以内に「準確定申告」が必要です。
所得税や消費税の申告を行い、過不足分を精算します。
手続きをスムーズに進めるコツ

- チェックリストを作る
項目を書き出し、期限順に整理する。 - 戸籍・住民票のコピーを複数用意
多くの手続きで必要になるため、最初にまとめて取得しておく。 - 専門家に相談
税理士・行政書士・司法書士に相談すれば、相続や名義変更のサポートを受けられます。
まとめ|葬儀後の手続きは早めに準備を
葬儀後の手続きは多岐にわたり、期限があるものも少なくありません。
- 死亡届:7日以内
- 相続放棄:3カ月以内
- 準確定申告:4カ月以内
- 相続税申告:10カ月以内
まずは死亡届と保険・年金関係から進め、順に整理していくことがポイントです。
悲しみの中でも、必要な手続きを早めに済ませることで、故人の名義や資産を安心して次の世代に引き継ぐことができます。