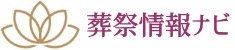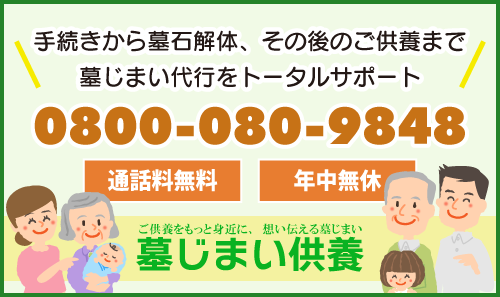一周忌・三回忌の違いと法要の進め方
[掲載日]2025/10/08 62 -

葬儀や四十九日法要が終わると、次に迎える大きな節目が「一周忌」と「三回忌」です。
どちらも故人を偲び、遺族や親族が集まる大切な法要ですが、「どんな違いがあるのか」「どのように準備を進めるのか」については意外と知られていません。
この記事では、一周忌と三回忌の意味の違い、時期、準備、当日の流れ、服装やマナーまでを分かりやすく解説します。
一周忌・三回忌とは?

一周忌とは
故人が亡くなってから 満1年目 に行う法要。
仏教において最も重要な年忌法要とされ、遺族・親族だけでなく友人や知人も招かれることがあります。
- 「忌明け」後、最初の大きな法要
- 故人を改めて偲び、感謝の気持ちを伝える場
- 一般的に「法要+会食(お斎)」を行う
三回忌とは
故人が亡くなって 満2年目 に行う法要です。
「三回忌=3年目」と思われがちですが、亡くなった年を「一回忌」と数えるため、実際は2年後に行います。
- 一周忌ほど大規模ではなく、親族中心
- 規模を小さくして自宅やお寺で行うことも多い
一周忌と三回忌の主な違い
| 項目 | 一周忌 | 三回忌 |
|---|---|---|
| 時期 | 亡くなってから1年後 | 亡くなってから2年後 |
| 招く範囲 | 親族・友人・知人など広め | 親族中心 |
| 規模 | 比較的大きい | 徐々に小規模化 |
| 準備内容 | 案内状・返礼品・会食などを丁寧に | 簡略化される傾向 |
| 意味合い | 初めての年忌法要 | 節目を締めくくる供養 |
法要の日程と時期の決め方
どちらの法要も、「亡くなった日を含めて満1年目/2年目」にあたる日を目安に行います。
ただし、参列者の都合を考慮し、命日の前の週末(土日) に行うのが一般的です。
例:
- 2024年3月10日逝去 → 一周忌:2025年3月8日または9日(土日)
- 同年 → 三回忌:2026年3月7日または8日(土日)
一周忌・三回忌の法要の流れ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1. 開式 | 僧侶が読経を始める |
| 2. 焼香 | 喪主・遺族・参列者の順に焼香 |
| 3. 法話 | 僧侶による説法や故人の思い出 |
| 4. 閉式 | 合掌・礼拝 |
| 5. 会食(お斎) | 供養の意味を込めた食事会 |
所要時間は全体で約1〜2時間程度です。
一周忌では僧侶の読経後に集合写真を撮ることもあります。
準備するもの一覧
| 準備項目 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 日程・会場 | 寺院・自宅・会館などを早めに予約 |
| 僧侶への依頼 | お布施・お車代・お膳料を準備 |
| 案内状 | 1か月前を目安に送付 |
| 香典返し・引き出物 | 香典の1/3〜半額程度の品を用意 |
| 会食(お斎) | 弁当・仕出し・会食場の手配 |
| 供物・供花 | 果物・花などを供える |
| 写真・位牌 | 故人の遺影や本位牌を飾る |
お布施・お車代・お膳料の目安
| 項目 | 金額目安 |
|---|---|
| お布施 | 3万円〜5万円 |
| お車代 | 5千円〜1万円 |
| お膳料(会食代の代わり) | 5千円〜1万円 |
僧侶へのお礼は、白封筒または奉書紙で包み、水引は「双銀結び切り」を使います。
服装マナー(遺族・参列者)
| 立場 | 服装 |
|---|---|
| 喪主・遺族 | 正喪服(ブラックフォーマル) |
| 親族・友人 | 準喪服または略喪服 |
| 女性 | 黒のアンサンブル・ワンピース |
| 子ども | 黒・紺・グレーの落ち着いた服装 |
夏は薄手のブラックフォーマルでも可。アクセサリーは黒真珠など控えめに。
会食(お斎)のマナー
- 故人を偲びながら、明るく穏やかに過ごす
- お酒は控えめに(乾杯ではなく「献杯」と言う)
- 長居せず、食事後は挨拶をして退出する
献杯の挨拶例
皆さま、本日はお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。
故人の在りし日を偲び、感謝の気持ちを込めて献杯いたします。
法要後に行うこと
- お礼の電話・手紙(参列者・僧侶へ)
- 香典返しの発送・手渡し
- 写真整理・法要の記録
- 次回(七回忌など)の目安を確認
よくある質問Q&A
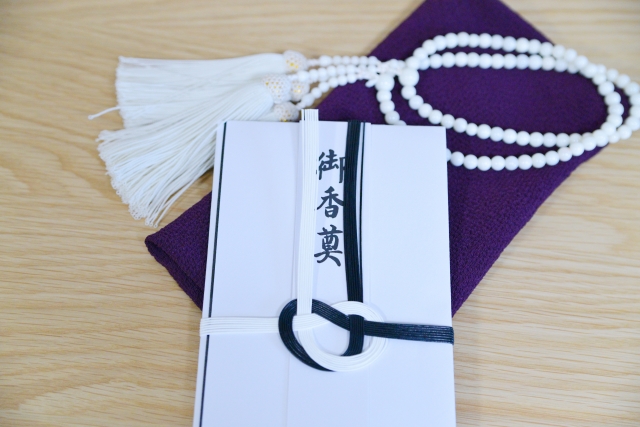
Q:一周忌と三回忌をまとめて行っても良い?
A:可能です。遠方の親族が多い場合など、日程調整の都合で「一周忌・三回忌合同法要」とするケースもあります。
Q:友人として参加する場合の香典は?
A:3千円〜5千円が一般的です。家族単位で参列する場合は1万円程度でも問題ありません。
Q:法要に出席できない場合は?
A:香典を現金書留で送り、手紙を添えて弔意を伝えるのが丁寧です。
まとめ|一周忌・三回忌は「感謝と節目」を伝える日
- 一周忌は「初めての年忌法要」
- 三回忌は「節目を締めくくる供養」
- 日程調整・僧侶依頼・返礼品の準備を早めに
形式よりも、「故人を想う心」と「家族・親族のつながりを深める時間」を大切にすることが、一番の供養になります。