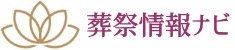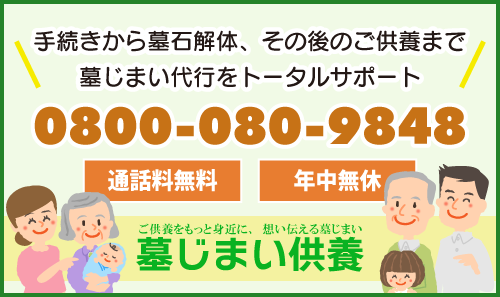初めて喪主を務める方へ|葬儀の基本的な流れと準備チェックリスト
[掲載日]2025/10/02 47 -

葬儀は誰もが一度は直面するものですが、多くの方にとって「喪主を務める」のは初めての経験です。大切な家族を亡くした悲しみの中で、式の準備や参列者への対応を担うのは大きな負担となります。
「何から始めればいいのか分からない」
「失礼のないようにしたいけれど、知識がない」
このような不安を抱える方のために、本記事では喪主の役割や葬儀の流れを時系列で整理し、必要な準備物やマナーをチェックリスト形式で解説します。これを読めば、初めてでも安心して喪主を務められるよう、全体像を把握できるはずです。
喪主の役割とは?

喪主が担う責任と立場
喪主とは、葬儀を主宰する人物であり、故人を代表して儀式を執り行う立場です。具体的には、葬儀社や僧侶との打ち合わせ、葬儀形式や規模の決定、参列者への挨拶、香典返しなど幅広い役割を担います。
最も重要なのは「遺族や親族、参列者をまとめる存在」であることです。喪主が落ち着いていることで、周囲も安心して式に臨むことができます。
喪主に選ばれる基準
一般的に喪主は以下の順で選ばれることが多いです。
- 故人の配偶者
- 長男
- その他の子ども(長女など)
- 孫や兄弟姉妹(場合によっては)
近年では「形式にこだわらず、最も近しい関係性の人」が務めるケースも増えています。
喪主が決まったらまずやるべきこと
喪主が決まったら、最初に取り組むべきことは次の3点です。
- 葬儀社に連絡を入れる
- 親族や関係者へ訃報を伝える
- 葬儀の日程や形式を大まかに決める
特に葬儀の日程は火葬場や僧侶の都合に左右されるため、早めの調整が不可欠です。
葬儀全体の流れを時系列で把握する
喪主を務める上で最も重要なのは「全体の流れを把握すること」です。以下では臨終から葬儀後の手続きまでを順番に解説します。
臨終直後の対応
- 医師から死亡診断書を受け取る
- 葬儀社に連絡し、遺体搬送を依頼
- 安置場所(自宅または葬儀社の安置室)を決める
【ポイント】
深夜や早朝でも葬儀社は24時間対応しているため、時間を気にせず連絡して問題ありません。
通夜までの準備
- 葬儀の日程を調整する
- 会場(自宅・斎場・寺院)を決定
- 僧侶への連絡と読経依頼
- 遺影写真の選定(必要に応じて加工)
- 会葬者リストの作成(香典返し数の把握に必要)
【例】
家族葬を希望する場合は、訃報を伝える範囲を限定する必要があります。「どこまで知らせるか」は喪主の判断で大きく変わるため、親族とよく相談しましょう。
通夜の流れと喪主の役割
通夜は告別式前夜に行う儀式で、参列者にとって故人と最後の別れを交わす場です。喪主の主な役割は以下の通りです。
- 式開始前に参列者を迎える挨拶をする
- 焼香や読経に参列者と共に臨む
- 通夜振る舞い(食事)の場で感謝の言葉を述べる
挨拶例:
「本日はご多忙のところ、父のためにお集まりいただき、誠にありがとうございます。どうぞ心ゆくまでお別れをしていただければ幸いです。」
告別式の流れと喪主の役割

告別式は葬儀の中心となる儀式であり、参列者が故人との最期の別れを告げる場です。喪主は、参列者を代表して故人に感謝を伝える重要な役割を担います。
告別式の主な流れ
- 開式の辞
- 僧侶による読経
- 弔辞・弔電の紹介
- 焼香(参列者・遺族)
- 喪主による挨拶
- 閉式の辞
喪主の挨拶例
「本日はお忙しい中、亡き母のためにご会葬いただき、心より御礼申し上げます。皆さまのお力添えをいただき、無事に式を執り行うことができました。今後とも遺族一同を温かく見守っていただければ幸いです。」
火葬・精進落としでの喪主の対応
出棺と火葬
出棺時には、喪主は遺族を代表して最後の挨拶を行います。火葬場では「収骨(骨上げ)」を行い、遺骨を骨壺に納めます。
精進落とし
火葬後に行われる食事の席が「精進落とし」です。ここでも喪主は簡潔に感謝を伝えます。
挨拶例:
「本日は最後までお付き合いくださり、誠にありがとうございました。故人も皆さまに見送られて安らかに旅立てたことと思います。」
葬儀後に必要な手続き
葬儀が終わっても、喪主には多くの事務手続きが残されています。
- 香典返し:四十九日を目安に発送
- 公共サービスの名義変更:電気・ガス・水道など
- 金融機関の手続き:口座凍結解除、相続関連
- 年金・保険の手続き:受給停止や給付請求
- 法要準備:四十九日、一周忌など
葬儀後1週間以内に、タスクを整理しておくと後々慌てずに済みます。
喪主が準備すべきものチェックリスト
喪主が用意すべきものを表に整理しました。印刷して使える実用的なチェックリストです。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 死亡診断書 | 医師から受け取る | 火葬許可証の申請に必要 |
| 火葬許可証 | 市区町村役場で発行 | 葬儀社が代行可 |
| 遺影写真 | Lサイズ以上 | 背景加工が一般的 |
| 会葬者リスト | 名前・住所・関係性を記録 | 香典返しに使用 |
| 祭壇・供花 | 宗派に合わせる | 葬儀社手配可 |
| 香典返し | タオル・食品・お茶など | 2,000〜5,000円相場 |
| 喪服・小物 | 男性:モーニング/女性:黒ワンピース | 靴・バッグも黒で統一 |
| 数珠 | 宗派ごとに異なる | 忘れやすい持ち物 |
喪主として知っておきたいマナー

喪服の基本
- 男性:黒のモーニングまたはブラックスーツ、黒ネクタイ、黒靴下
- 女性:黒のワンピースまたはアンサンブル、黒パンプス、光沢のないバッグ
- 子ども:中高生は制服、小学生以下は黒や紺のフォーマル服
弔問客への挨拶
葬儀では参列者への感謝を何度も伝える場面があります。難しく考える必要はなく、「本日は誠にありがとうございます」と一言添えるだけで十分です。
宗派ごとの作法
- 仏式:焼香(1〜3回、宗派により異なる)
- 神道:玉串奉奠(玉串を回して供える)
- キリスト教:献花(花を棺に捧げる)
宗派によって違いがあるため、事前に葬儀社や僧侶に確認すると安心です。
ケーススタディ:葬儀の形式別にみる喪主の役割
葬儀の形式によって、喪主の負担や役割は大きく変わります。代表的な3つのケースを見てみましょう。
家族葬の場合
参列者は親族や親しい友人に限定されるため、喪主の挨拶も簡潔で問題ありません。
- 訃報を知らせる範囲を限定する判断が必要
- 親族への説明責任(「なぜ家族葬にするのか」)が生じる
- 式後に参列を希望する人への対応を考えておくことが大切
一般葬の場合
参列者が数十名〜数百名になるため、喪主の負担は最も大きくなります。
- 式の前後に複数回の挨拶が必要
- 受付・香典返し・会葬礼状などの準備も増える
- 親族・知人への役割分担が必須
直葬(火葬式)の場合
通夜や告別式を省略し、火葬のみ行う葬儀形式です。
- 喪主の挨拶は火葬前後の簡単なものだけで済む
- 式の費用や準備は大幅に軽減できる
- 後日「お別れ会」や弔問希望者への対応が発生しやすい
喪主の負担を軽減するために
葬儀社に任せられることは任せる
祭壇の設置、参列者の案内、料理や返礼品の手配などは葬儀社に依頼できます。喪主は「全てを自分でやらなければ」と思い込まず、専門家に任せることが大切です。
親族・知人への役割分担
- 喪主:全体統括、挨拶
- 親族代表:受付対応
- 知人や友人:会場案内や記録係
このように分担を決めておくことで、喪主自身が式に集中できるようになります。
事前相談や葬儀保険の活用
最近は「生前相談」を利用して葬儀の流れや費用を把握する方も増えています。事前に準備しておくことで、喪主となった際の負担が大きく軽減されます。
まとめ|喪主を務めるときに大切な心構え

初めて喪主を務めると、不安や戸惑いで頭がいっぱいになるのは当然のことです。しかし、喪主に求められるのは「完璧な進行役」ではありません。
- 故人を想い、心を込めて見送ること
- 参列者への感謝を伝えること
- 自分一人で抱え込まず、葬儀社や親族と協力すること
この3つを意識すれば、初めてでも十分に立派な喪主を務められます。
「大切な人を送り出す」という役割は、決して簡単ではありません。ですが、あなたの真心が参列者に伝われば、それこそが故人への最大の供養となるはずです。