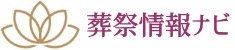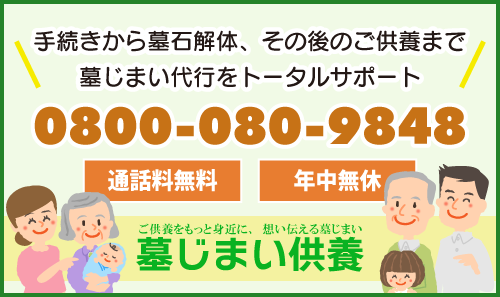四十九日法要とは?流れと準備するものを徹底解説
[掲載日]2025/10/07 77 -

葬儀が終わると、遺族にとって次の大きな節目となるのが「四十九日法要(しじゅうくにちほうよう)」です。
しかし、初めて喪主や遺族として準備を進める場合、何をすればよいのか、どんな流れなのかが分かりづらいもの。
この記事では、四十九日法要の意味から当日の流れ、準備するもの、服装やマナーまでをわかりやすく解説します。
四十九日法要とは?

四十九日法要とは、故人が亡くなってから49日目に行う仏教の法要です。
仏教の考えでは、人が亡くなるとすぐに極楽浄土へ行くのではなく、49日間をかけて閻魔(えんま)大王による裁きを受けるとされています。
そして、49日目に「来世の行き先」が決まる──その節目の日が「満中陰(まんちゅういん)」です。
このため、四十九日は「忌明け(きあけ)」とも呼ばれ、遺族にとって大切な区切りの日となります。
四十九日法要の目的
- 故人の冥福を祈る
- 遺族・親族が集まり、供養を行う
- 忌明けを迎え、日常生活に戻る節目とする
特に「位牌の開眼供養(魂入れ)」や「納骨式」を同日に行うケースが多く、実質的には“葬儀後の総まとめ”のような意味を持ちます。
四十九日法要の時期と日程の決め方
- 基本は「亡くなった日を含めて49日目」に行う
- 実際は、参列者の都合を考慮して49日目の前の週末に行うことが多い
- 僧侶のスケジュールを最優先で決めるのが鉄則
【例】
1月1日逝去 → 49日目は2月18日 → その週末(2月15日や16日)に法要を実施するのが一般的です。
四十九日法要の流れ
法要の進行は大きく分けて次の通りです。
- 開式・僧侶の読経
- 焼香
- 法話(僧侶によるお話)
- 位牌開眼供養・納骨(行う場合)
- 閉式・会食(お斎)
会場は自宅・寺院・斎場・納骨堂など、故人や家族の希望によって選びます。
四十九日法要の準備一覧
| 準備項目 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 日程調整 | 僧侶・親族・会場のスケジュールを確認 |
| 会場手配 | 寺院・自宅・会館などを予約 |
| 僧侶への依頼 | 読経と法要のお願い(お布施の準備) |
| 案内状送付 | 2〜3週間前を目安に親族へ通知 |
| 引き出物・返礼品 | 出席者に渡す品を手配(香典返しを兼ねる) |
| 食事(お斎)の準備 | 会場併設または仕出し弁当を手配 |
| 位牌・仏壇の準備 | 本位牌の手配、白木位牌からの魂移し |
| 墓地・納骨堂の確認 | 納骨を行う場合は石材店・霊園に連絡 |
法要の進行イメージ(当日スケジュール)
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 10:00 | 僧侶到着・準備 |
| 10:30 | 読経・焼香(約30分) |
| 11:00 | 法話・閉式 |
| 11:30 | 納骨式(行う場合) |
| 12:00 | 会食(お斎) |
| 14:00 | お開き・お礼挨拶 |
規模によって前後しますが、2〜3時間程度が一般的です。
四十九日法要に必要な持ち物

- 遺影写真・位牌・遺骨
- お布施(僧侶へのお礼)
- お供え物(果物・菓子など)
- 数珠・袱紗・香典袋
- 引き出物・返礼品
お布施の金額は地域・寺院によって異なりますが、一般的には 3万円〜5万円程度 が目安です。
香典・返礼品のマナー
- 四十九日は「香典返し」の時期でもある
- 返礼品の相場は「香典の1/3〜半額」程度
- 名簿を作り、誰に何を渡したかを管理する
最近では「カタログギフト」や「高級お茶・お菓子」が人気です。
服装マナー(参列者・遺族)
| 立場 | 服装 |
|---|---|
| 喪主・遺族 | 正式喪服(ブラックフォーマル) |
| 親族・参列者 | 準喪服または略喪服 |
| 子ども | 黒・紺・グレーなど落ち着いた服装 |
アクセサリー・ネイル・香水は控えめに。
会食の際も着替えずに喪服のままで問題ありません。
法要後の挨拶例
法要や会食後、喪主が代表して挨拶を行います。
本日はお忙しい中、四十九日法要にお集まりいただき、誠にありがとうございました。
皆さまのおかげをもちまして、無事に忌明けを迎えることができました。
故人もきっと安らかに眠っていることと思います。今後とも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。
四十九日法要後に行うこと
- 仏壇への本位牌安置
- 納骨(墓地・納骨堂など)
- 忌明け挨拶状の送付
- 香典返しの発送・手渡し
このタイミングで「喪中はがき」や「相続関連書類」なども整理しておくとスムーズです。
まとめ|四十九日は「区切り」と「感謝」の日

四十九日法要は、単なる儀式ではなく「故人への感謝と、日常への一歩」を象徴する日です。
- 日程は亡くなった日から49日目を目安に
- 僧侶・会場・参列者の準備を早めに行う
- お布施・返礼品・会食の手配を忘れずに
心を込めた準備と丁寧な対応が、故人への最大の供養になります。